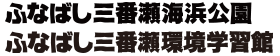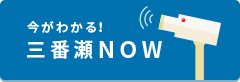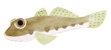友の会専用ページ 2021年6月
- トップ
- 友の会専用ページ 2021年6月
ふなばし三番瀬環境学習館 友の会専用ページ 6月号
超初心者の干潟観察方法
本年度、三田中学校から環境学習館に来ました新人の吉野です。
小学校の校外学習など学校・団体連携を担当しています。理科教員をやっていたのですが、干潟とは縁がなく、なかなか生きものを見つけられませんでした。
これでは校外学習下見の時に困ったと思っていたところ、先輩が干潟研修を企画してくれ、長靴を履いて干潟に出かけました。そこで教えてもらった生きものを見つけるための何気ないテクニックを紹介します。
コツ1しばらく動かない。甲長や甲幅が1㎝のコメツキカニにとって175㎝の私は巨大な怪獣に見えているでしょう。じっと私が立ち去るのを待っているのです。特にコメツキガニは振動に敏感だそうです。しばらくじっとしているとにょろにょろ動き出した貝を発見しました。アラムシロという巻貝でした。


コツ2しゃがんで見る。立って上からのぞいてもなかなか気づかないものです。低く近い位置から見ると変化に気づきやすいです。
底生生物は隠れるのが上手です。砂に擬態をする魚たちもいます。(擬態について詳しくは学習館2階へ)

コツ3痕跡に注意。巣穴の形や大きさ、穴の周りの砂団子、鳥の足跡など生きものの暮らしを示すものがいっぱいあります。そこを狙うようにしましょう。
この痕跡については学習館1階の巣穴とそこに棲む生物の展示がとても参考になりました。


コツ4スコップは素早く。砂を掘り上げる際は一気に行いましょう。逃げ足の早い生きものばかりです。敵に食べられないよう、必死に逃げているのです。

コツ5これだけは覚えよう。干潟には多くの生きものがいて、すべてを覚えようとしてもなかなかできないものです。
親御さんや先生も子供に名前を聞かれて困った経験があるのではないでしょうか。でも大丈夫です。三番瀬でよく見つけられる代表的な生きものを3つ挙げてみました。この3つをまず教えてあげてください。きっと喜んでくれると思います。
題して「超初心者のための船橋三番瀬いろいろベスト3」
カニの仲間部門 1位コメツキガニ 2位マメコブシガニ 3位オサガニ
エビ、ヤドカリ部門1位ユビナガホンヤドカリ 2位ニホンスナモグリ 3位アナジャコ
魚部門 1位ボラ 2位マハゼ 3位ヒメハゼ
鳥部門 1位ハマシギ 2位コサギ 3位ミヤコドリ
植物部門 1位ハマダイコン 2位ハマヒルガオ 3位トベラ




コツ6復習も大切。学校での勉強と同じに復習も大切です。観察終了後、図鑑を見てみましょう。パラパラっとめくるだけでも構いません。そして見つけた生きものには付箋を貼ってみましょう。付箋の数が増えるとなぜかうれしいものです。生きものの名前も自然と覚えられます。

干潟観察後は必ず長靴を洗います。砂や汚れを学習館に持ち込まないだけでなく、干潟にいる菌やバクテリアなどを部屋に持ち込まないためだと先輩は教えてくれました。干潟の生態系を陸上に持ち込まない、自然環境を守る意味もあると解釈しました。
最後に子どもと大人が共に発見し共に学ぶ場がふなばし三番瀬環境学習館です。多くの方のご来館を楽しみにしています。